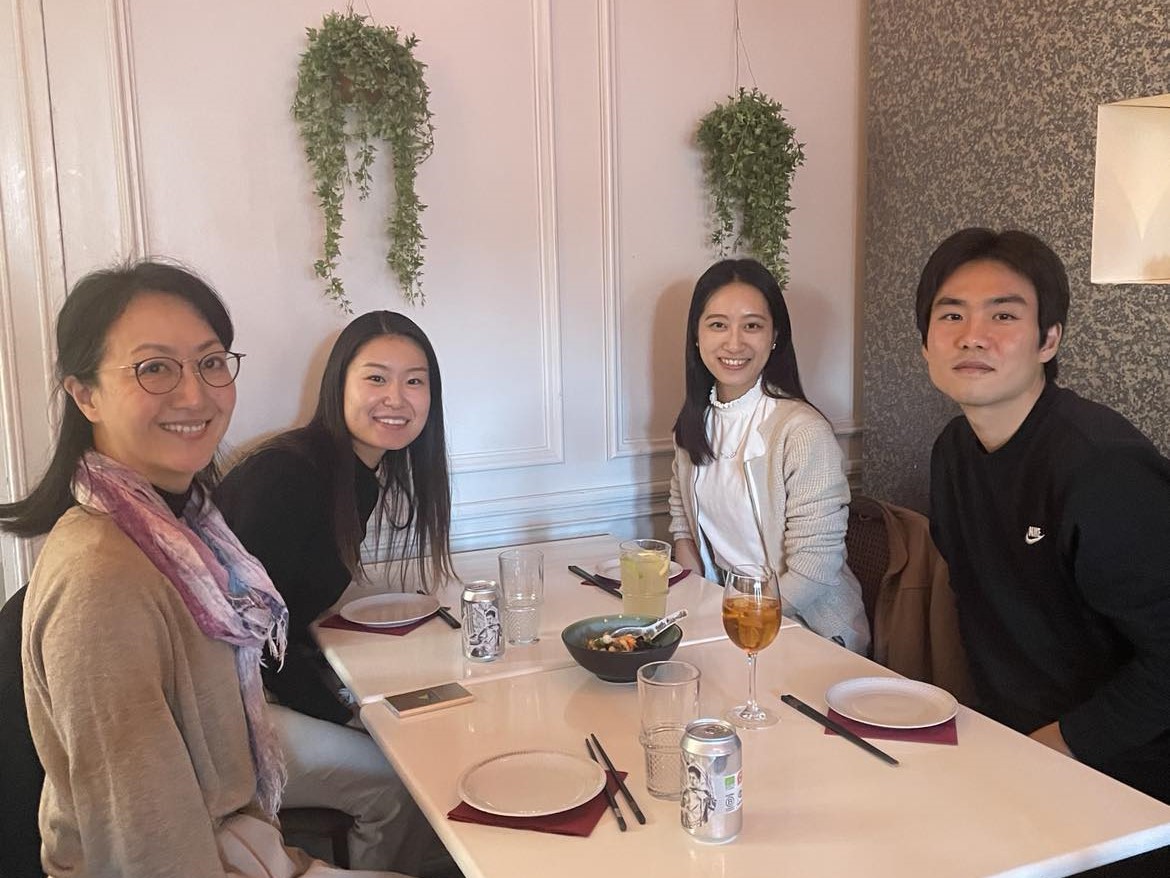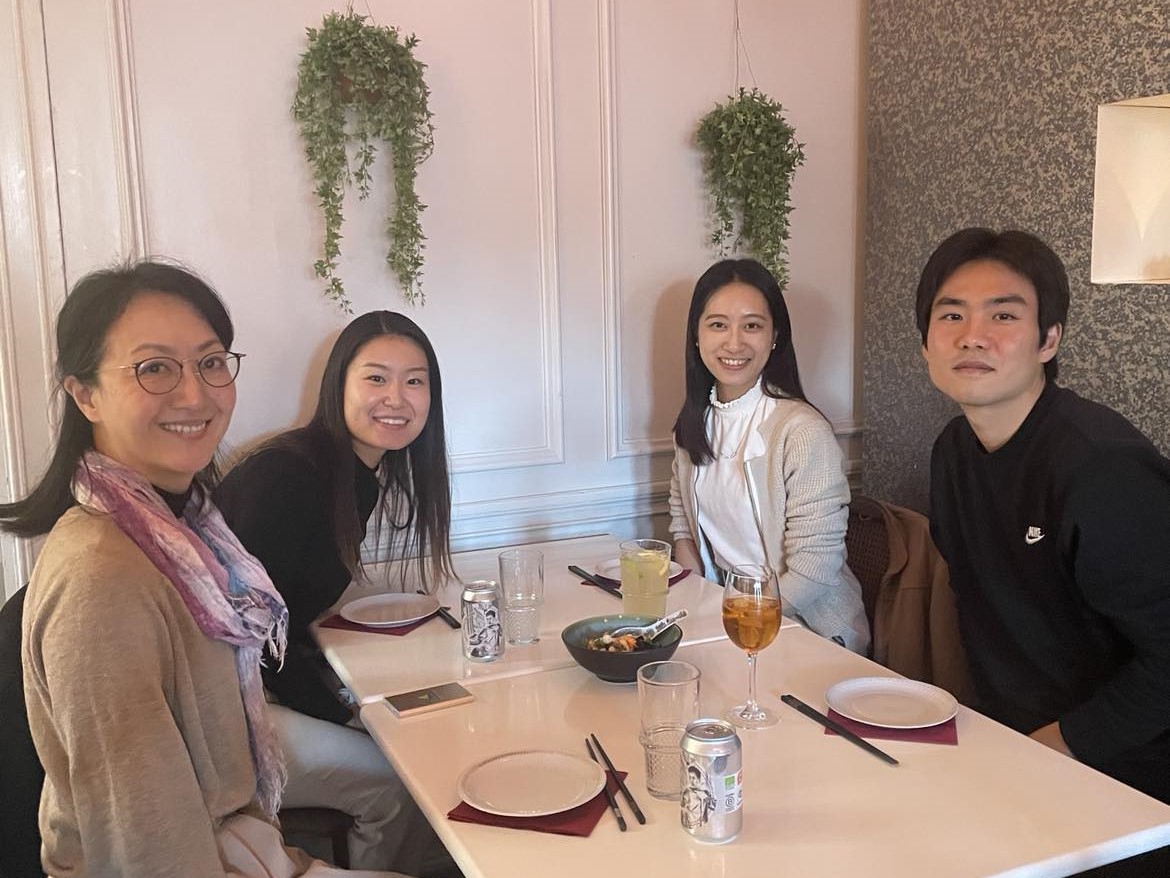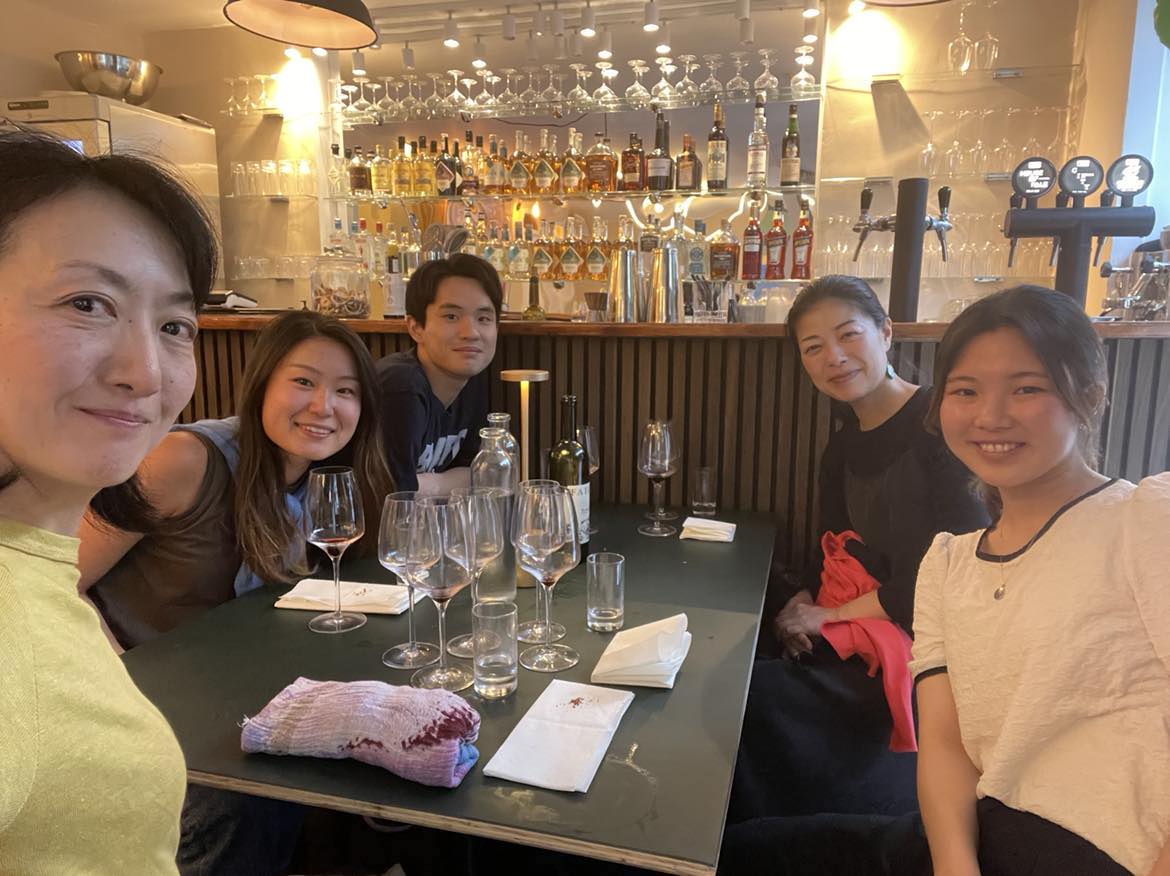私は2023年9月から2024年2月までの6ヶ月間、北欧研究所でインターンをさせていただきました。
北欧研究所での活動は、初めて触れる業務ばかりで思うように行かず大変な思いをすることも多くありましたが、大学の座学だけでは知り得なかったであろうデンマーク社会の多くの側面に触れ、社会情勢の変化をより身近なものとして体感することが出来ました。私が個人的にインターン開始時に立てた目標のひとつであった、「北欧社会を批判的に捉える」ということも、タスクを通して大いに実践することが出来ました。
具体的な業務としては、スタートアップの調査、スマートシティとしてのコペンハーゲン視察の計画・アテンド、福祉制度の調査、XとFacebookの運用に携わらせていただきました。これらの業務を通して、全く専門外であったとしても英語・もしくはデンマーク語の原典に向き合って調査する粘り強さや、デンマーク社会を対外的に発信する際の他者視点を鍛えることが出来たと考えています。このような貴重な経験が出来たことは、私の留学生活にとってかけがえのない財産となりました。
また日々の委託業務に加えて、私自身の個人研究にも取り組ませていただきました。「デンマークにおける包括的性教育とジェンダー観形成の関係性」というテーマで、現地のNGOにインタビューを行ったり、学生へのアンケート調査を行ったりしました。
安岡さんや同僚の方々にアドバイスを受けながら研究を進め、日本に帰国してからも少しずつ書きためて、ようやく1つのレポートとして充実した内容にすることが出来ました。成果を発表させていただく場を持てるということは大変希有なことで、私としても留学の集大成として書き上げることができ安堵と感謝の気持ちでいっぱいです。
実は、働き始めて間もないころ、安岡さんが「留学先で得られる繋がりの尊さ」についてお話ししてくださったことがありました。「これがしたくて自分は遠路はるばるここまで留学に来たんだ、だから力を貸して欲しい」ということを信念を持って伝えれば、予想できなかった繋がりも実現できる。留学生の信念や熱意に人は動かされるものだ。というお話でした。
私はそのお話を聞いてから、留学して得られる環境は一生に1度だと胸に刻んでその環境を利用しまくろう、頼りまくろう、自分のコンフォートゾーンを抜け続けようと決心しました。その結果として、レポートに協力くださった方々だけでなく、教育現場やクリニックへの訪問・インタビューなど多くのご縁に繋がり、留学が何倍にも実りの多いものになりました。このように私の留学中の姿勢や方向性を正しアドバイスをくださった安岡さんには感謝の気持ちでいっぱいです。このインターンに参加したことにより、自分の信念に立ち返りながら目的意識を持って留学生活を過ごせたと思っています。
そしてもう一つ重要なことは、コミュニティとしてこのインターンの場は非常に私にとって心安まる空間だったということです。同僚の方々との気の置けない会話や業務外での交流を持てたことにより、留学中のストレスや悩みを解消しながら過ごすことができたのだと思います。
これら全ての貴重な経験ができましたのも、代表の安岡さん始め他のインターン生、業務で関わってくださった全ての方々とのご縁があってこそだと思っております。この場をお借りして厚く感謝申し上げます。
いつか胸をはってまた皆様にお会いできるよう、これからの自分の研究やライフワークに努め、精進したいと思います。
本当にありがとうございました。
小野愛莉